1995年エッセイ・入選
『保険は病いの鎮静剤』
愛知県 (匿名希望)
44歳
|
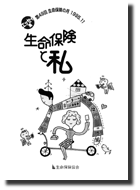
|
私が癌であることを告知されたのは、平成七年三月七日の夕方です。胆石の疑いで検査入院してから三週間ほど後のことです。担当の医師から検査結果の説明があるとのことで、病院の一室に妻とともに通されました。
「あなたの病気は癌です」という言葉に、一瞬、目の前が真っ白になりました。医師の説明では、癌は末期の膵臓癌であり、肝臓にも転移しているので手術は不可能であること、そして、私の命は長くて一年、短ければ三ヶ月しかないということでした。
もし癌であれば告知するようにと、日ごろから妻に言っていた私ではありますが、さすがに大きなショックを受けました。まだ四十四歳の私が本当に癌であることが信じがたく、言葉も出ず、ただぼう然としていました。病室にもどり妻と二人だけになると、涙があふれて止まりませんでした。
自分の死を見つめて、その夜は眠れませんでした。一番心配なことは、三人の娘のことです。下の娘はまだ五歳です。妻はひとりで育てていくことができるでしょうか。そして、年寄り二人をかかえて経済的にやっていけるのでしょうか。あれこれ考えると、やり切れない気持ちになります。そんな時、これまで何気なく入っていた生命保険が、私の心の動揺を静めてくれました。保険金は残された家族にとっては十分な金額ではないかもしれまぜんが、病人である私にとっては心休まる鎮静剤となりました。
|