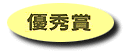父の一周忌が過ぎ、やっと母が遺品の整理を始めた。そんな時、大東亜戦争必勝祈念と書かれた生命保険の証券が私の目に留まった。その表紙をめくると、配当付き養老保険で払込み金額八拾弐圓拾八銭也、保険金弐千圓也と記載されていた。 農学校を出たばかりの十八歳の父が南方農業開発指導で海軍嘱託の小スンダ民政部に赴任する昭和十九年六月、「お金を使うこともない所だから」と初給料四拾弐圓を祖父に渡し、佐世保の軍港を後にしてバリ島へ赴いた。その一週間後、祖父はすべてを保険に当てたのだと言う。それから二十五年も経った昭和四十四年、被保険者である父のもとに、保険会社の社員が満期金額二千円をわざわざ持って来て、腹をかかえて大笑いしたと、母は当時のことを懐かしく思い出しながら語ってくれた。 兵隊として前線で戦う訳ではないのだが、やはり戦時下である。祖父は万が一と思って掛けたのだろうか。今では直接聞き出すことは叶わないが、「無事に帰ってこい」という父親が我が子を思う絆のようなものを、私はこの書面から何となく感じとった。そして祖父と同様に、その父も「一人前の男になったら、必ず保険にかたらんばいかん」の口癖で、私のために十八歳から大学院を修了するまでコツコツと払っていてくれたことを思い出した。 この古びた保険証券は母から私に手渡された。この時、私は家族の絆も託されたような思いであった。 
|