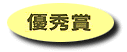父が他界したのは私が二十才の時。亡くなる少し前、「保険がおりるから」と繰り返すので、そんなこと言わないでと責めたことがある。父は目を閉じ、声をたてずに泣いていた。 先日、母に「あの預金で旅行にでも行ってくればいいのに」と言うと、すぐに拒まれた。母はこれまで父の死亡保険金に手をつけたことがない。 「今までやってこられたのは、あのお金のおかげよ。 ギリギリに追い詰められるまでは絶対に使うまいって、 がんばってきたんだから」 母の言葉に、父の顔が浮かんだ。 「天の上でぼやいているかもよ。『俺がせっかく遺してやったのに使いもしない。かわいくないヤツだ』って」 母は笑いながら、首を横に振った。 「でも、すごく感謝してるわ。いざとなったら引き出せるお金があるって大きな支えよ」 その言葉を聞いて、私はあることを思い出した。父に保険のことを言うのはやめてと訴えたあの日、付き添いの方に言われたのだ。「お父さんは家族に『支え』を遺したい一心なのよ」と。そういえば、大黒柱たる者にこだわり、とにかく私たちを守ってくれる人だった。 父の想いはしっかりと生きている。保険のお金を一円たりとも使わないことが、母を今まで支えてきたのだ。父が遺したお金をあてにするのではなく支えにしてきた母、これからも強く堅実に生きていくに違いない。我が家の大黒柱はやはり永遠に父のようだ。 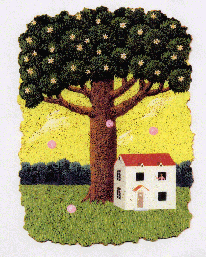
|