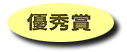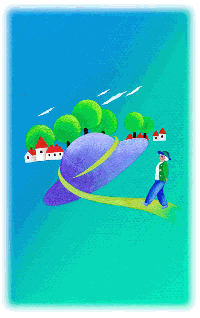姑は、もう七十七歳。散歩のお供は、折りたたみができる軽い帽子だ。コートやワンピースの色に合わせて、ワインレッド、グレー、ベージュ、と各色取り揃えている。 高度成長期をわき目もふらずに働きつめた義父の傍らで、姑は生命保険の営業職員として、家族の生活を支えてきた。雪国生まれの真っ白い肌を強い日差しから守るために、そのときも帽子はなくてはならないものだったろう。 退職後、義父はきっぱりと隠居生活に入り、姑と夫婦で旅行を楽しむはずだった。リタイアした姑も、日よけのための実用品だった帽子をおしゃれ用のものに買い替えて、やっと訪れた平穏な日々を楽しむ予定だった。しかし、実際には、日よけ帽をかぶって、姑は大学病院に看病に通ったのだ。 それから六年。義父はとうとう敢無くなってしまったけれど、いまの姑の暮らしぶりは実に穏やかだ。充分に看病したという満足感もさることながら、何でも相談し合ういい夫婦だった義父母は、互いに互いを受取人として生命保険に加入していたのだ。 経済的な安心感がこんなにも残された人の穏やかな日々を保障するのかと、しみじみ思う。 今日も姑は日課の散歩に出たことだろう。営業職員時代に鍛えた健脚で、日よけ帽をかぶってガシガシ歩く姑。昔のお客さんと日向で話し込むこともままあるらしい。 お義母さん、あなたにはその帽子がお似合いです。 いつまでも元気でいてくださいね。
|