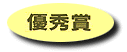高校三年生の冬、漁師だった親父はお袋と三人の子どもを残して死んだ。強い西風にあおられて、親父の小さな伝馬船はいとも簡単にひっくり返ったという。助ける間もなく親父は波の中に消えていったと聞かされた。 もともと稼ぎのある漁師ではなかったから、親父を亡くした一家の生活はすぐに苦しくなった。僕が真剣に高校をやめることを考え始めたその矢先、神棚に祭る大黒様の足元に一枚の証券がはさまれているのをお袋が見つけた。 それは親父の生命保険だった。親父が亡くなる十年前から支払われているもので、受取人の欄にはお袋の名前が記されていた。 酒とタバコが大好きだった親父は少ない小遣いの中から保険料を毎月捻出していたのだ。胸が締め付けられる思いだった。親父の生命保険が一家を救ったのだ。 あれから二十五年、親父が死んだ年齢を僕は迎えようとしている。僕は親父を超えることができるだろうか。父親として、そして、夫としてこれからの僕は何をすべきなのだろうか。 朝焼け色に染まる東京湾に僕は今日も漁の無事を祈るのだった。
|