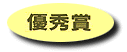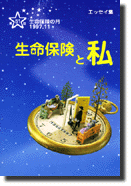六十才を過ぎた母が病に倒れたのは、もう十年も前のことである。いったんは入院したが、「家にいたい」と退院してきた。たまたま会社勤めを辞めていた私が自然に家事と母の世話を引き受ける形になった。それなりに大変な日々が続いたある日、母が生保の人を呼んでほしいという。生命保険の受取人を私にするというのだ。生保の人がきて手続きをするあいだ、母は不自由な身体をシャンと伸ばし、しっかりと応対した。 すべての処理が終わり、証券が出来上がると母はそれを私に持っているように言った。しまっておくのではなく、文字通り持っていることを要求した。「盗まれるといけないからね」…私はエプロンに大きなポケットを付け、証券を入れて母に見せた。「いつもここに入れてるから」・・・「よし」とでもいうように、母は大きくうなずいた。一生の大事を終えたかのように、その後の母は床についたきり、赤子に戻った。 それから二年後、母が眠るように最期を迎えたときも、証券は私のポケットにあった。 お守りのようにいつも持っていたそれを握り締めて、私は泣いた。 額はといえば、勤めていたときのお給料数カ月分である。が、母の気持ちを思うとき、それははかり切れないほどの重みを持った。 お金はその後私が自分を取り戻し、再出発するまでの資金として役立たせてもらった。 母の思い出は、今は心のポケットにある。 |