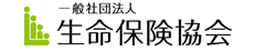生命保険協会は、指定紛争解決機関であると聞きますが、指定紛争解決機関とはどういった機関ですか。また、指定紛争解決機関の特長(利用のメリット)は何ですか。
-

-
- A1-1:
- 当会は、保険業法に基づく生命保険業務に関する指定紛争解決機関(※1)です。国の認可を受けた指定(外国)生命保険業務紛争解決機関業務規程
 に基づく運営を行っています。
に基づく運営を行っています。
指定紛争解決機関の主な特長(利用のメリット)は、次のとおりです。
1.中立・公正性、専門性
- 法令上の要件(経理的基礎・技術的基礎、役職員の公正性、業務規程の内容の十分性等)を満たして、国から指定を受けたADR機関ですので、中立・公正な業務運営が行われています。
- 苦情解決手続を行う生命保険に詳しい専門の相談員を東京本部(生命保険相談室)の他に連絡所(全国51箇所)に配置しています。
- 紛争解決手続を行う裁定審査会委員には、金融・保険分野の知識・実務経験を有する弁護士、消費生活相談員、生命保険協会(生命保険相談室)職員が就任しており、いずれの委員も個別の生命保険会社と特別な利害関係を有しない中立・公正な第三者です。また、裁定審査会事務局にも、金融・保険分野の法令に関する専門的知見、生命保険商品・実務に関する専門的な知識を有し、個別の生命保険会社と特別な利害関係を有しないスタッフを配置しています。
- 裁定審査会での手続にあたり、当事者(申立人、生命保険会社)と特別な利害関係を有する裁定審査会委員は、当該裁定案件の手続・審理に参加することができない仕組みになっています。
- 指定紛争解決機関の業務の公正・円滑な運営を図るため、外部有識者の委員で構成される裁定諮問委員会を設置し、業務運営に関する検証・評価を行い、委員からのご意見等を参考に運営改善や利便性向上に努めています。また、同様の目的で、裁定審査会に申立てをされた申立人および相手方保険会社を対象に、苦情解決手続を含めた手続面に関する利用者アンケート(感想、意見等)を実施しています。
※裁定諮問委員会の開催状況、検証・評価結果は、「相談所リポート」 をご覧ください。
※利用者アンケートの実施については、<Q5-5>を参照。
- 指定紛争解決機関の監督官庁は、金融庁であり、定期的に業務実施状況等の報告を行っているとともに、法令にもとづく検査や行政処分等を受けることもあります。
2.簡易・迅速性
- 裁定審査会は、生命保険協会(生命保険相談所)の東京本部に設置していますが、裁定申立て後、審理にあたっては主に書面により事実確認等を行いますので、全国どこからでも手続が可能です。
お客さま(申立人)に対して事情聴取(裁定審査会委員によるトラブル発生時の状況や主張内容のヒアリング)を行う場合は、お近くの連絡所(各道府県に設置)にてテレビ会議システムを利用することもできます。
- 迅速な解決を図ります(1件あたりの手続期間は、申立て受理後、裁定審査会の結果通知に至るまで平均約5ヶ月です)。
3.手続の実効性
- 手続の相手方となる生命保険会社には、(1)お客さまから苦情申立てや裁定申立てがあった場合の手続への参加義務、(2)苦情解決や裁定審理に必要な資料提出や説明等の協力義務、(3)裁定審査会が提示した裁定結果(和解内容等)への受諾義務(一定の場合を除く)が課せられており、消費者保護の観点からADR手続の実効性確保のための措置が図られています。
4.手続の非公開
- 裁定審査会の手続は、裁判手続とは異なり、非公開であり、お客さまのプライバシーが十分に守られるように運営しています(当会における苦情解決手続や裁定審査会を通じて入手したお客さまの個人情報等は、苦情解決手続や裁定審査会の紛争解決手続に必要な範囲内でのみ利用いたします)。
- そのため、お客さま(申立人)においても、裁定審査会を通じて入手した情報(例:相手方保険会社の答弁書、反論書、証拠書類、裁定書、和解契約書など)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。
トラブル解決を図るため保険会社と交渉していますが、問題の解決が難しく、交渉は平行線のままであり、裁定審査会への申立てを考えています。どこに連絡すればよいですか。また、申立てはいつでもできますか。
-

-
- A1-2:
- まずは、生命保険相談所へご連絡ください。
- 生命保険相談所では、生命保険に詳しい専門の相談員より、お客さまが生命保険会社との間で解決に向けて話し合うためのアドバイスを行います。それでも解決されず、苦情解決のお申し出を受けた場合は、相手方保険会社に連絡(解決依頼)を行います(当相談所は保険会社に対し解決に向けたアドバイスを行ったり、対応等を促しますが、当相談所がお客さまの代理人となって会社と交渉していく手続ではありませんので、ご留意ください)。
- 解決依頼後、原則として1ヶ月経過しても問題が解決しない場合には、保険会社の対応状況を確認のうえ、お客さまの申立てのご意向に応じて、裁定審査会事務局より、所定の「裁定申立書」の用紙を送付します。なお、すでに相手方保険会社との交渉が十分になされ、当事者間での解決が困難であると認められる場合には、会社との対応状況を踏まえ、1ヶ月を待たず「裁定申立書」の用紙を送付します。
- 裁定審査会に申立てを行う場合には、まずは、当会(生命保険相談所)における上記の苦情解決手続を経ることが必要(申立要件)であり、同手続を経ず、直接、裁定審査会に申し立てることはできませんので、ご留意ください。
裁定審査会による紛争解決(裁定)手続は、どのような法令や規定に基づき実施していますか。
-

-
- A1-3:
- 生命保険業務に関する指定紛争解決機関である生命保険協会は、<Q1-1>のとおり、保険業法に基づくADR機関(指定紛争解決機関)です。具体的な手続については、指定紛争解決機関として保険業法により作成が義務付けられている指定(外国)生命保険業務紛争解決機関業務規程
 や、同規程の細則である新裁定審査会運営要領
や、同規程の細則である新裁定審査会運営要領 に基づき実施しています。
に基づき実施しています。
裁定審査会の審理体制、裁定審査会委員の構成について教えてください。
-

-
- A1-4:
- 裁定審査会は、7つの部会から成り、各部会は弁護士、消費生活相談員、生命保険協会(生命保険相談室)職員各1名の合計3名の委員で構成されています。各部会で決定した裁定結果等については、原則、全委員(弁護士7名、消費生活相談員7名、生命保険協会職員3名の合計17名)で構成される全体会で再度の審理を経て最終決定を行っており、各部会の判断にバラつきが生じないよう、裁定審査会は2層体制で運営しています。
- 裁定審査会委員には、金融・保険分野の知識・実務経験を有する弁護士、消費生活相談員、生命保険協会(生命保険相談室)職員が就任しており、いずれの委員も個別の生命保険会社と特別な利害関係を有しない中立・公正な第三者です(裁定審査会委員の人選の際には、中立・公正な立場で判断ができるか等委員としての適性を確認するための面談を実施したり、委員委嘱後生命保険会社と継続的な利害関係を有するに至った場合は委員を辞任する等の誓約書を徴求するなど、中立性・公正性について十分に配意した手続を行っています)。
- また、生命保険協会(生命保険相談室)職員の委員は、生命保険会社の出身者でなく、生命保険協会のプロパー職員です。
- 全委員で構成される全体会は、裁定結果等の最終決定の他に、委員間で公正かつ適確な裁定審査会手続の実施のために必要となる情報・知識(金融ADR関係の動向、新規の保険商品、当会作成の自主ガイドライン、利用者アンケートの実施結果等)を共有する場としても活用しております。
※裁定審査会の部会長(弁護士委員)の一覧はこちらをご覧ください。
裁定審査会への申立てが受理されない場合はありますか。どのような場合に受理されませんか。
-

-
- A1-5:
- 裁定審査会は、裁定審理を開始する前に、申立人から提出された「裁定申立書」および証拠書類等の内容に基づき、申立内容を受理すべきか否かについて適格性の審査を行います。審査の結果、次の事項に該当すると裁定審査会が判断した場合には、申立てを受理せず、申立人宛てその理由を明記した「不受理通知書」の通知(郵送)をもって、手続を終了することになります。
【裁定手続を行わない申立内容】
-
1.
生命保険契約等に関するものでないとき。
-
2.
申立人が生命保険契約等契約上の権利を有しないと認められるとき。
-
3.
確定判決または確定判決と同じ効力を有するものと同一の紛争であるとき。
-
4.
申立人が、相手方保険会社と知識情報力または交渉能力の格差等がないものと認められるとき。
-
5.
不当な目的でみだりに裁定の申立てをしたと認められるとき。
-
6.
当事者以外の第三者が重大な利害関係を有し、当該者の手続的保障(主張・立証の機会)が不可欠であると認められるとき。(※1)
-
7.
過去に裁定審査会において判断が示された申立内容であるとき。
-
8.
他の指定紛争解決機関において審理継続中または審理が終了したものであるとき。
-
9.
会社の経営方針や職員個人に係る事項、事実認定が著しく困難な事項など、申立内容が、その性質上裁定を行うに適当でないと認められるとき。(※2)
(※1)
「6.当事者以外の第三者が重大な利害関係を有し、当該者の手続的保障(主張・立証の機会)が不可欠であると認められるとき」とは、例えば、生前、保険契約者(兼被保険者)が死亡保険金の受取人変更手続を行い、変更後の受取人に対し死亡保険金が支払われた後に、死亡した被保険者の相続人が、受取人変更手続の取消しと、変更前の受取人である自己への保険金の支払を請求するような場合(この場合、変更後の受取人が第三者にあたります)などです。
(※2)
「9.会社の経営方針や職員個人に係る事項」とは、例えば、保険会社の業務内容・制度等の改善措置や会社内部資料の開示等を求めるものや、職員個人(会社組織を含む)への処分や謝罪、慰謝料の支払を求める場合などです。また、「9.事実認定が著しく困難な事項」とは、例えば、契約申込当時の契約者の意思能力の有無が問題となる場合や、筆跡鑑定を求める場合、当事者以外の第三者への証人尋問手続が審理上必要となる場合など、裁判所における訴訟手続によることが適切であり、厳密な証拠調手続をもたない裁定審査会において裁定を行うには適当でないと判断する場合などです。
過去に申立てが受理されなかった事例については、不受理事案の概要をご覧ください。
裁定審査会に申立てを行う場合、「裁定申立書」の用紙はどのように入手できますか。また用紙入手後、提出期限はありますか。
-

-
- A1-6:
- 当会における苦情解決手続<Q1-2参照>を経ても当事者間での解決が難しい場合、申立てのご意向を確認のうえ、裁定審査会事務局より、所定の「裁定申立書」の用紙を郵送しますので、到着後1ヶ月以内に作成・提出いただくことになります。なお、ワープロソフト等を利用して作成される場合には、その旨申出がありましたら、送信専用のEメールにて用紙(フォーム・Wordソフトのみ)を送信します(ただし、裁定申立書等のEメールでの送付・提出はできません)。
- 申立書用紙の送付の際には、裁定審査会手続の流れや留意事項、申立書作成要領、記入例等を分かり易く記載した「裁定審査会ご利用の手引き」を同封いたしますので、<Q2-1>のとおり、同手引きを参考に申立書の作成や書類等のとりまとめを行っていただくことになります。
- 申立書用紙到着後、申立人から裁定審査会事務局に対し、事前に遅延の連絡がなく、1ヶ月経過しても裁定申立書等の提出がなされない場合は、お申し立ての意思がないものと判断させていただき、苦情解決手続を終了し、その旨書面にて通知いたします(この場合でも、その後、事前にご連絡のうえ裁定申立書等の提出があったときは、紛争解決(裁定審査会)の手続を進めます)。
当事者ではなく家族や知人から申し立てることもできますか。また、申立人の代理人になれる者の範囲を教えてください。
-

-
- A1-7:
- 申立ては、原則として、生命保険契約等に基づく権利者本人が行ってください。例えば、保険金等に関する申立てはその受取人が、契約の効力等に関する申立ては、保険契約者が申立人になります。なお、法定代理人(成年後見人、親権者等)や代理人弁護士による申立ては可能です(この場合、成年後見人・親権者等であることの公的証明書、弁護士への委任状の提出が必要です)。
※弁護士を代理人に委任する場合であっても、裁定審査会の手続が有利に進められることはありません。
なお、身体等の障害により申立人本人が手続を遂行することが困難であると裁定審査会が認めたときには、申立人の配偶者や三親等内の親族に限り、申立人の代理人になることができます。この場合、裁定審査会所定の「代理人申請書兼委任状」および関係書類を裁定申立書とともに提出いただく必要があり、同申請書(申請理由等)に基づき裁定審査会にて代理人申請の審査を行います(審査にあたり必要な書類等の提出を求める場合もあり、裁定審査会の判断により認められない場合があります)。
法人として申し立てることはできますか。
-

-
- A1-8:
- 法人を契約者や保険金・給付金受取人とする生命保険契約の場合、申立てを行うことができる者(申立権者)は、当該法人になります。この場合、申立てにあたり、裁定申立書や必要書類の他に、当該法人確認の公的証明書として法人の登記事項証明書の提出が必要となります。
裁定審査会の紛争解決手続は、『裁定型』と聞きますが、『裁定型』の手続とはどういった手続ですか。
-

-
- A1-9:
- 『裁定型』とは、紛争解決委員(裁定審査会委員)が当事者双方(申立人、相手方保険会社)から提出された申立書、答弁書、反論書や証拠書類等の書面、および当事者双方(申立人、募集人等)への事情聴取(委員によるヒアリング)に基づき、トラブル発生時(保険加入時や保険金請求時等)の事実関係の確認を行い、必ずしも法令や約款に基づかない柔軟な解決に向けて保険会社側に考慮すべき事情(保険会社・募集人の不適切な対応等)があるか否かなども踏まえて審理を行い、申立ての内容について理由を付して一定の結論を出し、これを当事者双方に提示する手続をいいます。
裁定審査会が、当事者双方の互譲(歩み寄り)による解決をあっせんする『調停型』ではなく、『裁定型』による手続を採用している理由は、生命保険制度は、大勢の人が公平に保険料を出し合い、保険事故が発生したときに保険金・給付金を受け取るという、助け合い・相互扶助の仕組みで成り立っており、全ての保険契約者は公平・平等に扱われなければならず(契約者平等の原則)、契約内容は生命保険約款により一律に定められていること(附合契約性)に拠ります。また、生命保険契約では、保険事故が生じた場合、支払保険料を超える多額の保険金等が支払われるため(射倖契約性)、制度が不正に利用されるおそれがあり(モラルリスクの存在)、それを防止することが生命保険制度の健全な運営のためには不可欠となります。このような生命保険の特性を踏まえ、裁定審査会では『裁定型』の紛争解決手続としています。
裁定審査会に申し立てれば、何らかの和解案は提示されるのですか。
-

-
- A1-10:
- 裁定審査会の紛争解決手続は、『裁定型』<Q1-9参照>ですが、<Q3-8>のとおり、裁定審査会の審理結果として、「和解案を提示する場合」の他に、「申立内容を認めるまでの理由がないと判断する場合」や「事実認定の困難性などの理由から、裁定審査会による手続ではなく裁判等での解決が適当である等と判断し、裁定手続を打ち切りとする場合」がありますので、必ずしも、申立て内容どおりの解決や何らかの和解案が提示されるものではありません。
裁定審査会は、生命保険会社や募集人に対しトラブルを起こした責任の追及や指導・監督、処分等を行ってくれますか。
-

-
- A1-11:
- 裁定審査会は、申立てが受理された紛争案件について、個別に紛争解決に向けて裁定の手続を行うことを目的としています。したがいまして、紛争(トラブル)の原因を作った生命保険会社や募集人等に対し責任追及や指導・監督等を行うことはありません。なお、裁定申立てが受理されない場合は、<Q1-5>のとおりです。具体的には、申立内容が保険会社の業務内容・制度等の改善措置や会社内部資料の開示等を求めるものや、職員個人への処分や謝罪、慰謝料の支払を求める場合などは、申立てが受理できないことがあります。
裁定申立てにあたり、費用はかかりますか。
-

-
- A1-12:
- 裁定審査会の利用(申立て)に際して、利用手数料はかかりません。ただし、裁定審査会の事情聴取に出席する場合の交通費、その他手続に関する費用(申立書等の郵便代・コピー代、電話代、書類等を準備するための費用など)は、お客さま(申立人)の負担になります。
裁定審査会での手続の内容や提出した書類、裁定の結果等については、公表されますか。
-

-
- A1-13:
- 裁定審査会の裁定手続は非公開ですので、提出された書類や裁定の結果等を含め公表いたしません。
そのため、お客さま(申立人)においても、裁定審査会を通じて入手した情報(例:相手方保険会社の答弁書、反論書、証拠書類、裁定書、和解契約書など)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。相手方保険会社においても同様です(なお、法令上の根拠があり、かつ裁定審査会が正当と認めた場合は除きます)。
ただし、裁定審査会では、手続について広く一般消費者等に周知し中立・公正性を担保することや同種案件の苦情・紛争の再発防止・未然防止を図るため、お客さまのプライバシーに配慮したうえで裁定案件の概要を当会ホームページで公表しております。このため、お申し立て時に裁定概要の公表について申立人等の同意を必ず得ています(同意いただけない場合は、申立てを受け付けない場合があります)。
裁定審査会への申立てにあたり、過去に裁定審査会で取り扱った案件の状況を確認したいのですが、今までの裁定案件の概要を教えてください。
-

-
- A1-14:
- 過去の裁定案件の概要は、裁定審査会が取扱った事案の概要をご覧ください。
なお、お客さまのトラブルと同種の裁定案件があったとしても、裁定審査会の判断の基礎となる事情(事実関係など)は案件毎に様々です。よって、裁定審査会は、裁定申立書や当事者双方から提出された書類等に基づき、個別の案件としてあらためて審理を進めることになりますので、必ずしも、過去の同種の裁定案件と同様な裁定結果に至るとは限りませんので、ご留意ください。
現在、保険会社と訴訟・民事調停を行っているトラブルがあります。訴訟・民事調停中のトラブルでも裁定審査会に申立てはできますか。
-

-
- A1-15:
- 生命保険相談所(裁定審査会を含む)の利用は、訴訟や民事調停の手続と平行して行うことも可能です。ただし、訴訟や民事調停、仲裁等により、同じ紛争案件において確定判決または確定判決と同じ効力を有するものが申し立てられたと裁定審査会が判断した場合には、<Q1-5>のとおり申立てを受理できませんので、ご留意ください。
トラブルに関連して生命保険会社に訊ねたいことがあります。裁定審査会への申立てを通じて、生命保険会社に対する申立人の疑問点や質問に、会社から回答してもらうことができるでしょうか。
-

-
- A1-16:
- 裁定審査会は、個別の紛争解決をはかる手続ですので、質問等への回答を求めることを目的とするものではありません。申立人が相手方生命保険会社に対する質問事項等を裁定申立書等に記載された場合に、どのように対応・回答するかは、保険会社において判断するものであり、裁定審査会が関与(回答要請等)することはありません。
ただし、裁定審査会が裁定審理に必要と判断した場合には、その範囲内で、申立人の疑問点や質問と同じ事項について、相手方生命保険会社に確認する場合があります。
裁定審査会への申立てには、「裁定申立書」や必要書類を作成・収集・提出することが必要とのことですが、不慣れで専門的な保険の知識もないなか上手く作成できるか不安です。誰でも作成できますか。
-

-
- A2-1:
- 「裁定申立書」には、申立内容やその理由・根拠となる事実等を記入していただきます。記入・作成方法については、裁定審査会事務局が「裁定申立書」の用紙を郵送する際、申立書の作成要領や記入例、留意事項、必要となる添付書類リスト等の説明用書面(裁定審査会のご利用の手引き)を同封いたしますので、同書面に基づき作成、書類等のとりまとめを行っていただくことになります。記入方法や作成にあたり確認したい事項、不明な点等があった場合には、直接、裁定審査会事務局宛てお問い合わせいただければ、担当者がわかりやすくご説明いたします。
【参考:裁定申立書の記載事項】
裁定申立書等を受け付けた後、裁定審査会事務局にて書類の確認を行います。申立書や添付書類等に不備・不足等があり、事務局よりその補正・補充を求められたときには、相当の期間内に提出いただく必要があります。正当な理由なく、相当の期間内に対応いただけない場合は、申立てを受け付けないこととし、裁定開始の手続を終了させていただくことがあります。
「裁定申立書」をワープロで作成することもできますか。
-

-
- A2-2:
- 裁定審査会事務局より、所定の裁定申立書用紙を受領後、ワープロソフト等を利用して作成される場合は、裁定審査会事務局にご連絡いただければ、送信専用のEメールにて用紙(フォーム・Wordソフトのみ)を送信いたします(ただし、裁定申立書等のEメールでの裁定審査会への送付・提出はできません)。<Q1-6参照>
裁定審査会への申立てにあたって、必要な要件(同意事項等)はありますか。
-

-
- A2-3:
- 裁定の申立てを行うに際し、申立人は指定(外国)生命保険業務紛争解決機関業務規程
 にもとづく紛争解決手続を行うことに同意し、次の項目について、申立人を含めて契約関係者(契約者、被保険者、受取人)全員の同意を得て、「裁定申立書」表紙の同意欄に押印いただいたうえで、提出いただく必要があります。
にもとづく紛争解決手続を行うことに同意し、次の項目について、申立人を含めて契約関係者(契約者、被保険者、受取人)全員の同意を得て、「裁定申立書」表紙の同意欄に押印いただいたうえで、提出いただく必要があります。
-
1.
申立人ならびに相手方保険会社(生命保険募集人を含む)が保有する契約関係者(契約者、被保険者および受取人(これらの者の相続人、代理人を含む)、以下同じ)に関する個人情報を裁定審査会の求めにより提供すること。ただし、申立て内容が団体信用生命保険契約にかかる場合は、契約者(金融機関等)が保有する契約関係者に関する個人情報を含むものとする。
-
2.
裁定審査会の審理において必要な場合に、一般社団法人生命保険協会が当該事案に係る医療行為の確認・照会等を目的に業務委託した機関ならびに契約者・被保険者の受診した医療機関、当該業務委託機関が同様の目的で確認・照会等を行う医師と医療機関に対し、契約者・被保険者に関する資料を提出のうえ、確認・照会等を求めること。
-
3.
裁定審査会が申立人より提出された裁定申立書、証拠書類等を相手方・保険会社に交付し、相手方・保険会社が裁定審査会に提出する答弁書等を作成するために、これらを利用すること。
-
4.
裁定審査会がプライバシーに配慮したうえで裁定手続を実施した全ての裁定概要(申立取下げ事案を除く)を公表すること。
-
5.
裁定審査会の裁定手続は非公開であることを認識し、裁定書等の書面や和解の内容を含め裁定手続に係る内容・書類について、方法・手段の如何を問わず、当事者以外への開示または公表はしないこと。
-
6.
申立人(代理人を含む)が裁定審査会の求める釈明や証拠等の提出または手続の遂行など審理に協力すること、および審理の進行を妨げる行為(委員および事務局を威迫するまたは侮辱する等により、裁定手続を妨害しまたは同手続に著しい支障を及ぼす行為を含む)を行わないこと。
なお、上記同意事項について正当な理由なく同意いただけない場合は、申立てを受け付けないこととし、裁定開始の手続を終了させていただくことがあります(また、裁定開始後、上記「5.」「6.」にかかる行為等がなされたことが確認できたときは、裁定審査会の判断により、裁定手続を打ち切りとさせていただく場合もあります)。
「裁定申立書」と一緒に提出する必要書類等とはどのようなものですか。
-

-
- A2-4:
- 必要書類としては、申立ての理由・根拠となる事実についての証拠書類、申立てを行う生命保険契約の保険証券(コピー)、申立人の本人確認ができる運転免許証・パスポートなどの公的証明書(コピー)があります。提出すべき証拠書類(※)とは、例えば、保険加入時のトラブルであれば、契約申込書や告知書の控え・パンフレット・設計書等の募集資料や保険会社からの説明書面・回答書面など(いずれもコピー)が考えられます。
なお、申立人が法人の場合、本人確認の公的証明書として当該法人の登記事項証明書の提出が必要となります。
申立人に代理人を立てる場合は、<Q1-7>のとおり、所定の委任状等の提出も必要となります。
証拠書類の例 |
どのような場合の証拠になりうるか |
約款
(申立にかかわる部分のみ) |
- 保険金、入院・手術等の給付金を請求する場合
- その他、約款の解釈が問題となる場合
|
募集時に受取った書類
- 申立契約の商品パンフレット
- 設計書(提案書)
- 意向確認書
- その他の案内
- 手書きのメモ
など
|
- 募集人から、どの部分を用いて、どのような説明を受けたという主張の裏付けとする場合
- 募集人による手書きの書き込みなどがあり、それが不適切な内容である場合
- 配当金等の金額に関して主張する場合
- その他、説明内容に関する主張をする場合
|
契約申込書
その他契約関係書類 |
- 契約が適切に締結されていないことを主張する場合(例えば、自分の筆跡でない、契約内容が説明と違うなど)
- その他、申込手続に関する主張をする場合
|
| 告知書 |
- 告知をするにあたり、募集人に不適切な行為があったなど、告知の方法や内容について主張する場合
|
| 相手方保険会社からの説明書面・回答書面など |
|
診断書、入院・手術証明書
医療記録
|
- 保険金、入院・手術等の給付金を請求する場合
- 診断書の内容に関する主張をする場合
- 入院時の状況に関する主張をする場合
|
| 預金通帳など |
- 保険料等が引き落とされていた(もしくは引き落とされていなかった)、振込があった(もしくはなかった)、当時の金融資産の状況などについて主張する場合
|
| その他 |
- 上記を参考に、主張の裏付けとなる資料があれば添付する
|
証拠物として録音データ媒体(USBメモリ等)を提出できますか。
-

-
- A2-5:
- 原則、録音データ媒体(USBメモリ、DVD等)のみでの受け付けはいたしません。録音内容を証拠物として裁定審査会に提出される場合は、必ずデータ内容(会話内容等)を書面に書き起こしたうえで、提出いただくことになります。
申立人は高齢で判断能力も不十分のため、「裁定申立書」の作成や必要書類の収集等が困難です。家族でも、本人の委任状があれば代理人になれますか。
-

-
- A2-6:
- 申立人に代理人を立てる場合の取扱いは、<Q1-7>のとおりになります。
ただし、法定代理人以外の代理人(申立人の配偶者、三親等内の親族)に委任する場合には、申立人本人に意思能力(代理人への委任能力)が存在することが必要となります。
- その際、裁定審査会所定の「代理人申請書兼委任状」および関係書類の提出が必要となります。
- なお、同申請書記載の代理人の「申請理由」によっては、裁定審査会の判断によりその確認のために必要な協力(診断書の提出等)を求めることがあります(確認の結果、裁定審査会の判断により申立てが認められない場合や、成年後見人等からの申立てが必要となる場合があります)。
申立人になるべき者が既に亡くなり、相続人として申立てを行う予定ですが、どのような手続や書類が必要ですか。
-

-
- A2-7:
- この場合、申立人は、「生命保険契約上の権利を有する者」(申立権者)の相続人がなり、次の手続・書類が必要です。
- 相続人の「相続関係を表す図」を作成のうえ、相続人の中から代表者1名を選任し、他のすべての相続人からの委任状および印鑑証明書を「裁定申立書」に添付いただくことになります(相続人全員からの委任状等の添付が無い場合は、裁定の申立てを受け付けないこととし、裁定開始の手続を終了させていただくことがあります)。
- 合せて、相続人全員が確定でき、他に相続人がいないことを確認できる戸籍謄本等公的証明書の提出も必要となります(提出された証明書類のみで不足する場合には、裁定審査会事務局より他の証明書類も含め再度提出を求めることがあります)。
- なお、裁定審査会からの資料の送付や問い合わせ、裁定書の通知等の手続は、原則、上記の選任された代表者に対して行うことになります。
どのような方法で審理されるのですか。
-

-
- A3-1:
- 裁定申立書等を受け付けた後、裁定審査会による申立内容の適格性の審査<Q1-5参照>を経て申立てが受理された場合は、相手方保険会社から申立書等に対する答弁書等の提出を求めたうえで、双方から提出された書類に基づき、紛争に至った事実等を確認し審理を行います。また、トラブルの実態や原因・背景、当事者の主張内容等を的確に把握することにより解決の糸口を見出すため、当事者(申立人、募集人等)に対して個別に面談により事情聴取(委員からのヒアリング)を行います。
※事情聴取を希望されない場合は、裁定申立書の中にその旨記入いただくことになります。ただし、当事者の主張内容や事実関係が明白でないと裁定審査会委員が判断した場合には、「希望しない」と記入されていても、事情聴取をご案内することもあります。
事情聴取を実施する場合、裁定審査会は、生命保険相談所の東京本部(生命保険相談室)で開催されますが、遠隔地のお客さまについては、最寄りの連絡所(各道府県に設置)に出向いていただき、テレビ会議システムを利用して裁定審査会委員による事情聴取を実施することもできます。
裁定審査会の標準的な審理手続の流れについて、教えてください。
-

-
- A3-2:
- 審理手続については、紛争解決(裁定)手続の流れを参照ください。
申立てが受理された場合、裁定手続終了までにどのくらいの時間がかかりますか。
-

-
- A3-3:
- 裁定審査会では、申立ての内容に応じた審理手続を行いますので、審理期間について一概にお示しできませんが、1案件あたりの手続期間は、申立て受理後、裁定結果の通知に至るまで平均約5ヶ月です(短い案件で約3ヶ月、長い案件では1年近く期間を要する場合もありますが、迅速な審理に努めています)。
今回のトラブルで大変困っています。お願いすれば審理手続を優先的に進めてもらえますか。
-

-
- A3-4:
- どの申立案件も公平・平等に取り扱っておりますので、特定の案件について優先的に取り扱うことはできません。
保険加入時の募集人との間の「説明した・説明していない」、「約束した・約束していない」等がトラブルの争点となっています。客観的にそれを証明するものがない場合、どのように審理されますか。
-

-
- A3-5:
- 裁定申立てにあたっては、<Q2-4>のとおり、裁定申立書と一緒に、トラブル(紛争)の原因が分かる申立ての理由・根拠となる証拠書類を提出いただく必要があります。例えば、保険加入時の契約申込書や告知書の控え・パンフレット・設計書(提案書)等の募集資料や保険会社からの説明書面・回答書面などが考えられます。裁定審査会は、申立人や相手方保険会社から提出された書類に加え、トラブルの実態や原因・背景、当事者の主張内容等を的確に把握することにより解決の糸口を見出すため、申立人や募集人等への事情聴取(委員からのヒアリング)を個別に実施し、審理を行います。したがって、客観的な証拠書類等がなくても基本的には審理は可能です(ただし、例えば、20年前・30年前の契約で、契約申込時における募集人の説明内容・方法、申込書の筆跡等が問題(争点)となる場合は、事実確認の困難性などの理由から厳密な証拠調手続機能を持たない裁定審査会による手続ではなく裁判等での解決が適当である等と裁定審査会が判断し、裁定手続を打ち切る場合もあります)。
保険会社は、生命保険約款に定める規定を理由に、保険金・給付金の支払を拒否しています。こういった場合、どのように審理されますか。
-

-
- A3-6:
- 裁定審査会では、<Q3-1>のとおり、当事者双方から提出された書類(診断書、証明書、看護記録、カルテ、事故報告書、調査報告書等)や事情聴取(委員からのヒアリング)の内容に基づき、事実確認を行い、審理を行います。
保険金・給付金の支払対象については、生命保険契約は附合契約(※)のため、保険会社と契約を締結した生命保険商品の生命保険約款に拘束されますので、支払請求の原因となる保険事故(普通死亡、災害死亡、入院、手術、障害、通院等)が同約款に定める「支払事由」や「免責事由」の規定に該当するか否かについて、事実確認を行いながら総合的に審理します。
また、保険約款を適用すれば保険金等の支払ができない場合であっても、申立人や募集人等への事情聴取を実施することにより、募集時や契約の保全手続時、支払手続時における会社側の対応、個別事情(説明不足、誤説明等)も考慮し、和解提案を行う場合もあります。
なお、裁定審査会では、案件の内容により必要に応じて、保険事故の状況や入院・治療内容の妥当性、当該約款規定の該当性等について、当会が業務委託している医療専門機関(第三者機関)に照会を行ったり、申立人本人の同意を得て、申立人や相手方保険会社を経由して申立人(被保険者)が受診した医療機関に照会を行い、審理の参考にすることがあります。
裁定審査会に申立てのあった事案に対する和解に向けた考え方(審理スタンス等)について教えてください。
-

-
- A3-7:
- 裁定審査会では、ADR(裁判外紛争解決手続)の趣旨を踏まえ、法令や約款に重きを置くことなく、積極的に事情聴取を実施することにより、より柔軟な解決の糸口となる個別事情(保険会社側の不適切な対応)の把握に努め、それらをできるだけ考慮した積極的な和解提案を行っています。
具体的には、当事者(申立人、保険会社)から提出された書面の他、トラブルの実態や原因・背景、主張内容を的確に把握することにより解決の糸口となる個別事情を見出すため、当事者(申立人、募集人等)に対して面談による事情聴取(裁定審査会委員によるヒアリング)を行っています。また、保険金・給付金の支払に係る案件については、必要に応じて、死亡・疾病の原因や入院の必要性等について、当会が業務委託している医療専門機関(第三者機関)に照会を行ったり、申立人本人の同意を得て、申立人や相手方保険会社を経由して申立人(被保険者)が受診した医療機関に照会を行い、より柔軟な解決の糸口を把握するための参考にすることがあります。
裁定の結果はどのような方法で示されますか。また、裁定結果にはどのような種類がありますか。
-

-
- A3-8:
- 裁定審査会にて審理した裁定結果について、その理由を具体的に明記した「裁定書」または「裁定打切りの通知」という書面にて、当事者双方(申立人・相手方保険会社)宛て通知(郵送)することで、裁定手続を終了します(口頭による結果の連絡や裁定審査会委員による説明等はありません)。
【裁定結果の種類】
- なお、裁定審査会では、当事者双方から提出された書面および事情聴取の内容を踏まえ裁定結果を判断しておりますが、「裁定書」および「裁定打切りの通知」は、必ずしも申立人・相手方保険会社の全ての主張等に触れるものではありませんので、ご留意ください。
裁定審査会を通して入手した情報等(相手方保険会社からの提出書類、裁定書、和解内容等)について、保険に詳しい知人にみせて相談に乗ってもらうことは、可能ですか。
-

-
- A3-9:
- <Q1-12>のとおり、裁定審査会の裁定手続は非公開です。そのため、お客さま(申立人)は、裁定審査会を通じて入手した情報(例:相手方保険会社の答弁書、反論書、証拠書類、裁定書、和解契約書等)を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできませんので、ご留意ください(なお、本件については<Q2-3>のとおり、申立てにあたっての要件(同意事項)の一つになっておりますので、仮に裁定審理中に第三者への開示やインターネット等への公開等の事実が発覚した場合には、裁定審査会の判断により裁定手続を終了させていただく場合があります)。
裁定審理の結果は、どのような方法で連絡(通知)があるのですか。
-

-
- A4-1:
- <Q3-7>のとおり、審理した裁定結果については、その理由を明記した「裁定書」という書面にて申立人宛て通知(郵送)いたします。また、事実確認の困難性などの理由から、裁定審査会による手続ではなく、裁判等での解決が適当である等と判断した場合は、その理由を明記した「裁定打切りの通知」という書面を申立人宛て通知(郵送)いたします(口頭による結果の連絡や裁定審査会委員による説明等はありません)。
【参考:裁定書の構成】
1.裁定の結論
2.裁定の理由
①事案の概要
②裁定審査会の判断(裁定手続の内容、裁定結果、裁定の理由、和解による解決とした事情等)
- なお、裁定審査会では、当事者双方から提出された書面および事情聴取の内容を踏まえ裁定結果を判断しておりますが、「裁定書」および「裁定打切りの通知」は、必ずしも申立人・相手方保険会社の全ての主張等に触れるものではありませんので、ご留意ください。
裁定審査会が提示した和解の内容には、必ず従わなければなりませんか。
-

-
- A4-2:
- 裁定審査会が和解案を提示するときは、<Q3-8>のとおり、その理由を明記した「裁定書(受諾勧告)」という書面にて当事者双方(申立人、相手方保険会社)に通知(郵送)し、当事者双方が和解案を受諾した場合は、和解契約締結手続を行い、和解成立となります(和解成立後は和解契約書記載の和解条項に従うことになります)。
提示された和解案の内容について納得がいかない場合は、同和解案を受諾しないこともできますが、当事者のいずれか一方が受諾しなかった場合には、裁定不調として手続終了(書面による通知)となります(ただし、相手方保険会社には、一定の場合(※)を除き提示された和解案を受諾する義務があります)。
- (※)「一定の場合」とは、(1)相手方保険会社が申立人が和解案を受諾したことを知った日から1ヶ月以内に同社から当該申立ての内容に係る訴訟が提起され、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき、または訴訟係属中の場合に当該訴訟が取り下げられないとき、(2)相手方保険会社が申立人が和解案を受諾したことを知った日から1ヶ月以内に当該申立ての内容について、当事者双方で仲裁法に定める仲裁合意がされたとき、または当該和解案によらずに別の和解や調停が成立したとき、がこれに該当します。
仮に裁定審理の結果について納得がいかない場合、再審理(再申立て)は可能ですか。他にトラブルを解決する機関等や保険に詳しい弁護士等を紹介いただけますか。また、再度、相手方保険会社と交渉等ができますか。他のADR機関への申立てや訴訟等はできますか。
-

-
- A4-3:
- 裁定審理の結果については、裁定書<Q4-1参照>に記載した内容が裁定審査会としての最終判断となり、再審理(再申立て)のご希望には応じかねます(裁定審査会は一審制であり、裁判のように上訴する機関は当相談所にはありません)。当会(裁定審査会)として、他のADR機関や弁護士等の紹介は行っておりません。また、その後の保険会社との交渉等についても、裁定手続が終了した当会(裁定審査会)として関知するものではありません。
他のADR機関への同じ申立内容での申立ての可否等については、当該ADR機関に直接ご確認いただくことになります。また、裁定審理の結果は、民事調停や訴訟手続に際し何ら制約を与えるものではありませんので、訴訟等の利用は可能です。
苦情解決手続や紛争解決(裁定)手続について、不満があります。このような生命保険相談所への苦情は、どのように申し出ればよいですか。
-

-
- A4-4:
- 苦情解決手続や紛争解決(裁定)手続について、不満や苦情等がある場合には、その概要を記載した苦情申出書を当会に設置された苦情処理委員会に提出することで、苦情の申出を行うことができます。ここでいう「苦情」とは、苦情解決手続における相談員の応対や紛争解決手続における手続面での苦情をいいます。従いまして、裁定審査会による裁定結果に関する苦情(納得できない等)は対象とはなりません。
- ※苦情処理委員会は、裁定結果を再審理する機関ではありませんので、ご留意ください(裁定審査会は一審制であり、裁判のように上訴する機関は当相談所にはありません)。
苦情処理委員会では、苦情申出書を受け付け後、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法について審議します。また、審議結果については、書面により申出者に通知することになります。
裁定審理の結果、和解で解決しなかった場合、申立内容の請求権の時効はどのようになりますか。
-

-
- A4-5:
- 指定紛争解決機関(生命保険相談所)利用の特長の一つに、「時効の中断」という法的効果があります。具体的には、申立ての請求内容については、裁定審理の結果、和解に至らなかった場合、裁定審査会からその旨の通知を受けた日から1ヶ月以内に訴訟を提起したときは、裁定審査会が申立てを受け付けたときに遡って、時効の中断事由が生じたものとみなされます。
裁定審査会に提出した書類等は申立人に返還されますか。
-

-
- A4-6:
- 指定紛争解決機関(生命保険相談所)は、裁定手続に関する書類や記録等の管理が必要とされていますので、提出された書類等は返還いたしません。ただし、申立人本人より返還のご請求があったときは、裁定審査会は写しを作成し、以後その写しを提出された書類等とみなして保管し、実際の提出書類等を申立人本人に返還いたします。
銀行(募集代理店)が販売した保険商品にかかる販売・勧誘時のトラブルの場合、生命保険に関するトラブルのため、ADR(裁判外紛争解決)機関としては生命保険協会の生命保険相談所(裁定審査会)の他には、申立てができないのですか。
-

-
- A5-1:
- 国から指定を受けた指定紛争解決機関としては、生命保険協会の他に、銀行業務に関する指定紛争解決機関である一般社団法人全国銀行協会(相談室、あっせん委員会)があり、同協会においても、苦情解決手続および紛争解決手続を行うことができます。生命保険協会での相手方会社は保険契約引受の生命保険会社となりますが、全国銀行協会での相手方会社は募集代理店の銀行となりますので、トラブルの責任の所在を募集を行った銀行とする場合や同一銀行で複数の保険会社の保険商品にかかるトラブルが生じた場合などは、全国銀行協会を申立先とすることをご検討ください。
なお、全国銀行協会での手続等については、同協会のHP を参照ください。なお、指定紛争解決機関以外の他のADR機関にも申立てを行うことができますが、申立てを受け付けるかどうかは当該ADR機関に確認いただく必要があります。
を参照ください。なお、指定紛争解決機関以外の他のADR機関にも申立てを行うことができますが、申立てを受け付けるかどうかは当該ADR機関に確認いただく必要があります。
平成19年9月以前に契約している簡易生命保険契約について、生命保険協会の生命保険相談所(裁定審査会)に申立てができますか。
-

-
- A5-2:
- 当会相談所で取扱いができる簡易生命保険契約に係る苦情・紛争事案は、当該事案が株式会社かんぽ生命保険の行う独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構からの受託業務(保険料の収納、契約の保全、保険金等の支払手続等の業務)に係るもののうち、申出内容がかんぽ生命のみを苦情解決手続または紛争解決手続(裁定審査会による裁定手続)の相手方当事者とするものに限られますので、ご注意ください。
平成19年10月以降のかんぽ生命保険との保険契約については、上記に関係なく、申立てを行うことができます。
国民生活センターに紛争解決委員会がありますが、どのような機関ですか。
-

-
- A5-3:
- 独立行政法人国民生活センターでは、その業務の一部として、国民生活センター法に基づく重要消費者紛争(消費者と事業者の間で起こる消費者紛争のうち、被害内容や事案の性質に照らし、その解決が全国的に重要であるもの)の解決を図る業務(紛争解決委員会による和解の仲介や仲裁)を行っています。同業務の手続等については、国民生活センターのHP
 を参照ください。
を参照ください。
指定紛争解決機関の他に、国が認証したADR機関として「ADR促進法」に基づく認証ADR機関がありますが、どのような機関ですか。
-

-
- A5-4:
- 「ADR促進法」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づくADR制度は、金融・保険に係るトラブル(紛争)を含めて国が裁判外の紛争解決手続(ADR)を行っている民間団体(弁護士会が運営する紛争解決センターなど)の業務を認証し、時効の中断効等の法的効果を付与するなど、ADRの利便性向上を図る制度です。本制度は、多様なトラブルの解決を対象としているため、対等な当事者間の平等な取扱いを強く意識した制度になっており、指定紛争解決機関による金融ADR制度の特長である、金融機関(保険会社、銀行等)に対する手続への参加や資料提出等の義務を、相手方の事業者には課していません。
「ADR促進法」に基づくADR制度については、法務省のHP を参照ください。
を参照ください。
生命保険相談所を利用した相談者に対してアンケートを実施していると聞いていますが、アンケートの実施状況等について教えてください。
-

-
- A5-5:
- 当会では、生命保険相談所をご利用いただいた方の率直な声(感想・意見・要望等)を今後の苦情解決手続および紛争解決手続の改善、利用者の利便性向上等に活かし、より中立性・公正性・利便性等の高い相談所業務運営(質的向上)を図っていくことを目的に、平成24年4月より、裁定審査会に申立てをされた方(申立人)や相手方の保険会社を対象(※)にアンケートを実施しています。
アンケートは、苦情解決手続を含めた、裁定審査会への申立て受付から裁定結果決定(通知)に至るまでの手続面に関する設問(感想、意見等)を中心としています。
- ※申立てが受理されなかった方、審理手続途中で打ち切りとなった方および申立てを取り下げた方等は、裁定結果までの最終手続まで至っていないので、アンケートの対象としておりません。
- ※申立人を対象にした利用者アンケートの実施状況および寄せられたご意見・ご要望を踏まえた当相談所の対応状況等は、
「相談所リポート」
 をご覧ください。
をご覧ください。